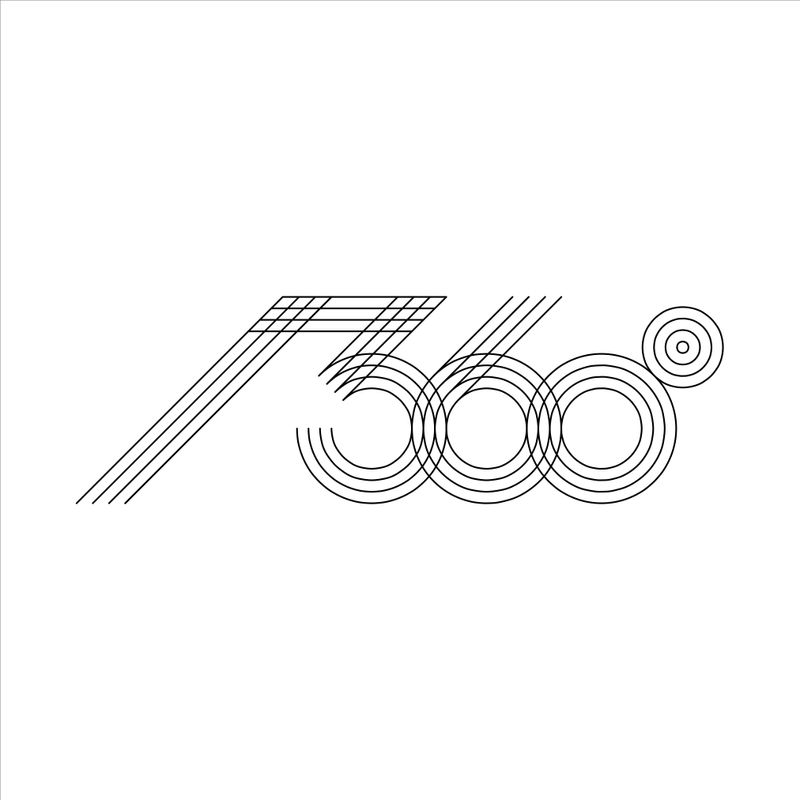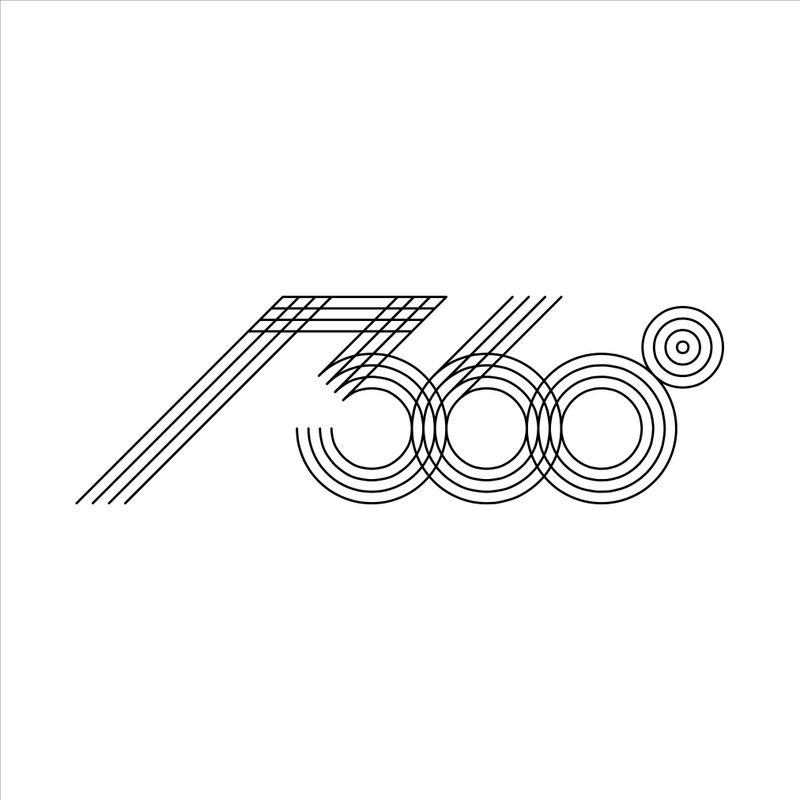
PROJECT MEMBER
数年前にスケッチを書いて、それを建てられる環境の敷地を探した。敷地があって、その条件を頼りに設計するのではなく、最初にスケッチがあったのだ。普段の作業とは全く逆の進め方であった。 自邸を建てるにあたり、ただ単に居場所をつくりたくて、今までの自分の中での住宅のあり方や、美しいと思うかたちを追い求めることなく設計をスタートさせた。それが本当に住みたいもののつくり方のような気がしたのである。結果いくつもの名前も付かないような場ができて、それは内だったり外だったり、狭かったり広かったり、クローズだったりオープンだったり、公園のようにヒエラルキーなく繋がって、レベル差も6種類になった。 1階は床レベルをGL-900mmにすることで、3,100mmの天井高に対して開放しつつもプライバシーを確保し、適度に籠った場をつくった。半地下にすることで安定した地中熱により夏は涼しく、冬は暖かい環境を手に入れた。土を掘ることによって土地の自重を軽くすることは、構造的にも有利になっている。 また、この建物は全体に軒が回っていて、日本の民家のように設備に頼らず快適さを確保しようと試みた。南側デッキの軒の深さは2,550mmあり、夏の強い日差しと雨をさけるために計画した。天井高も2,100mmに抑えていて、部屋の延長の場と言うよりも印象的には確実に部屋である。 さらに屋根の上には芝を植えることで、断熱効果を狙いながらもうひとつの居場所をつくっている。遊びの場を作るのではなく、暮らしていくうえである意味リアルに必要な場をつくった。居場所を内部と外部にきっちり分けて考えなかったように、芝屋根はこの敷地を越えて緑の多い近隣環境との間で境界を消すように溶け込んでいる。 必要な居場所で構成した結果、最終的に平面はボコボコとなったが、きれいな矩形に収めるようなことはしなかった。それは立面的にも断面的にも同じことで、屋根を境に1階と2階が別物に見えたり、壁が揃わなかったりする。 和でも洋でもなく、新しくも古くもない、どっちつかずで、なるべく編集しない、動物がただ巣をつくるような、目指すかたちをもたずに設計した。それが純粋で当たり前のことだと思ったし、本当のことだと思った。 最低限の欲とデザインで、偏ることなくなんの方向性も持たない建物「360°」にしたかった。それは改めて見てみると、ほぼファーストスケッチのまま完成していた。